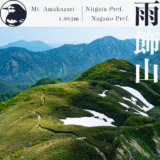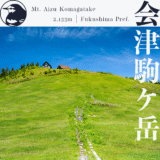田代山・帝釈山について
所在地:福島県
山系:帝釈山脈
標高:1,971m
選定:花の百名山・東北百名山・うつくしま百名山
所在地:福島県・栃木県
山系:帝釈山脈
標高:2,060m
選定:東北二百名山
田代山と帝釈山は福島県南会津町の南西部、栃木県との県境にまたがる帝釈山脈に連なる山々です。豊かな自然を誇る山域であり、尾瀬や会津駒ケ岳とともに尾瀬国立公園に指定されています。南会津の秘境中の秘境ともいえる帝釈山脈ですが、昭和の登山ブームの中で少しずつ名が知られるようになり、昭和48年には舘岩村と栗山村を繋ぐ「田代山スーパー林道」が開通したことでたくさんの登山客が訪れるようになりました。現在では登山道や木道が整備され田代山には避難小屋やトイレも設置されており、初心者でも気軽に登山を楽しむことができる山となっています。今回は台地状の平坦な山体に広大な湿原が広がる田代山と、鋭く突き出た山頂部から尾瀬や奥日光の山々を見晴らす帝釈山の二座に登りました。
広大な山頂湿原を持つ田代山

田代とは水田を意味し、転じて水が張り草花の繁茂する湿原を指すようになりました。尾瀬には○○田代と名付けられた湿原が幾つもあるので登山者にはお馴染みの名付けかもしれません。田代山は頂上に湿原が広がるまさに「田代」の山であり、台地状の山体の頂上に見渡す限り広がる広大な湿原が無二の景色を作り上げます。さらに湿原には雪解けの季節から多様な植物が咲き誇り登山道を彩ります。
田代山の歴史については福島県で制作している「ふくしま尾瀬」のホームページに詳述されていますのでご覧ください。秘境の山とは思えないほど整備の行き届いた田代山ですが、開山の歴史を伝える大師堂が今でも大事にされているというのは素晴らしいことだと思います。
帝釈山とオサバグサ

田代山と隣り合わせに聳える帝釈山脈の盟主、帝釈山。山全体を樹林帯に覆われた会津の深山らしい趣の山ですが山頂部は開けており、尾瀬や日光など近隣の山を始めとした素晴らしい展望を楽しめます。
『新編会津風土記』の会津郡「帝釈山」の項によれば
頂に大なる岩あり、土人駒神堂権現と称し年中参詣して隕霜五稼を害すること無らんことを祈誓す
花見朔巳 校訂『大日本地誌大系 第31巻 新編会津風土記』より(一部常用漢字に置換)
とあり、かつては信仰の山であったことが窺えます。この「駒神堂権現」の詳細は不明ですが檜枝岐村の会津駒ヶ岳、あるいは舘岩村で広く信仰されていた馬頭観音(会津には馬頭観音を祀る厩岳山の例がある)に関わるものなどと想像します。山名から考えれば帝釈天の可能性もあるでしょうか。見たところ現在の山頂には際立って大きな岩は無くお堂のようなものも無いので、山頂に何が祀られていたのかは推測するほかありません。湯ノ花集落には元々田代山登山口に祀られていた馬頭観音を村内に運んできたものが残っているらしく、もしかしたら帝釈山の御神体も麓の集落に移されて大事にされているのかもしれません。

帝釈山でも多様な山野草を見ることができますが、とりわけ帝釈山はオサバグサの群生地としてよく知られています。オサバグサはケシ科のオサバグサ属に分類される一属一種の日本固有種です。シダ植物のような櫛状の葉が特徴であり、これが機織り機の「筬(おさ)」に似ているので筬葉(おさば)草と名付けられました。6月頃になると花茎を20cmほど立てて白い花を鈴なりに咲かせます。あまり散在せず限られた山に群生する傾向にあるらしく、尾瀬では帝釈山と隣の台倉高山に集中的に分布し他の場所では稀なようです。帝釈山脈の尾根筋にはオオシラビソ林が分布しており、田代山から帝釈山へ向かう道中で針葉樹林の林床に群生している様子を見ることができます。
檜枝岐村方面の馬坂登山口では例年6月上旬にオサバグサ祭りを開催し記念バッジなどを配布していました。2025年からは帝釈山・台倉高山山開きに名前が変わりましたが記念バッジには変わらずオサバグサが大きく描かれています。名実ともに帝釈山を象徴する花であり、今回帝釈山に訪れた最大の目的がこのオサバグサです。
湯ノ花温泉・木賊温泉
田代山の北麓に位置する湯ノ花地区と木賊地区は個性豊かな秘湯が魅力の温泉地で、遠方から訪れる秘湯愛好家の方もいるという西会津町の名所です。テレビなどのメディアに度々取り上げられているので知っている方も増えてきたかもしれません。

湯ノ花温泉には4ヶ所の共同浴場があり300円の入浴券でそれら全てに入ることができます。弘法の湯を除いて洗い場の無い大変シンプルな造りのお風呂ですがいずれも贅沢な源泉掛け流し。ゆったりとした時間の流れる湯ノ花集落を散策しつつ、個性あふれる浴場巡りを楽しめます。

木賊温泉は数軒の旅館と2つの共同浴場から成る西野川沿いの小ぢんまりとした温泉地。中でも人気の共同浴場「岩の湯」は川縁に造られた半野生といってもいいような露天風呂で、その立地により幾度に渡り洪水被害を受けながらも地元の方々や温泉愛好家の尽力によって再建を果たしてきたという歴史あるお風呂です。開放的な浴場で川のせせらぎを聞きながら入る温泉は格別です。
猿倉登山口ルートについて
田代山・帝釈山 / 白雀さんの田代山・帝釈山の活動データ | YAMAP / ヤマップ
登山口は南会津から入る東側の猿倉登山口と、檜枝岐から入る西側の馬坂登山口の二つあります。いずれも駐車場までの林道は未舗装の山道です。猿倉登山口への道は未舗装でも整備は行き届いており平坦な砂利道といった感じです。大丈夫だとは思いますが車高の低い車は通行注意です。猿倉登山口の約400m手前にはトイレがあるのでこちらで済ませていくと安心です。ハイシーズンには登山口直近の駐車場が満車になることもあるので、その場合はトイレの駐車場から登ることもできます。
今回は猿倉登山口から田代山を通って帝釈山に登りピストンするルートで登りました。猿倉登山口から手前の小田代を通り田代山山頂湿原に向かいます。田代山の山頂湿原は周回路となっており反時計回りの一方通行なので注意してください。田代山湿原を通り過ぎると田代山避難小屋が建っておりトイレも整備されています。会津の奥地の山ではありますが全道に整備が行き届いており、危険箇所もほとんどないので天候が良ければ山に慣れていない方でも安心して登れる山だと思います。ただし田代山から帝釈山への道の頂上直下には岩場、はしご場があるので二座往復する場合は通行注意です。
猿倉登山口より先の栃木県日光市方面への道は通行止めになっているので通り抜け出来ず猿倉登山口へのアクセスは南会津町側のみになります。かなり長いこと通行止めになっているらしくいつ解除になるのかは不明です。また猿倉登山口へ向かう栗山舘岩線(旧田代山林道)は冬季(11月中旬~6月中旬ごろ)には通行止めになります。出発前に福島県のホームページで通行情報を確認することをお勧めします。
森を抜けて山頂湿原へ



田代山への林道入り口です。初っ端からいきなり未舗装というパンチの効いた道ですが道中は整備が行き届いており、危険箇所にガードレールが設置されていて比較的易しい山道でした。良質なフラットダートということでツーリングに訪れる方もいるようです。


猿倉登山口に着きました。橋を渡って森の中に入っていきます。

山道には階段が付けられているので楽に登れます。奥地の山ですが登山道の方も整備が行き届いています。

ゴゼンタチバナが見頃を迎えていました。地面が見えないほどの密度で群生しています。

田代山のゴゼンタチバナはかなり花が大きくて見応えがありました。

木陰にはギンリョウソウの親子が並んで咲いていました。木陰に咲くギンリョウソウはミステリアスな雰囲気です。


木漏れ日の気持ちいいオオシラビソ林を抜けると視界が開けてきます。



木々の隙間に張られた木道を歩いていきます。足元にはコバイケイソウやイワカガミといった高山植物が現れ始めます。



小田代に着きました。ちょうどワタスゲの綿毛が見頃を迎えており、たくさんの白いフワフワが風に揺れていました。

鮮やかなピンクのヒメシャクナゲも散見されます。


タテヤマリンドウやチングルマも顔を出しています。



小田代を抜けたらまた軽い登りです。アカモノやシロバナニガナが林に花を添えていました。


ロープ場を越えると再び開けた場所に出ます。上り坂で湿原の全体像が見えない辺りがニクい演出に思えてしまいます。
絶景広がる田代山の湿原歩き

帝釈山への道標が見えてきました。田代山頂上の湿原はすぐそこです。

道標に辿り着くと一気に見晴らしが良くなり、眼前一杯に広がる湿原に圧倒されます。

青と緑が視界を埋め尽くす見事な景色です。

ワタスゲ揺れる湿原の先にどっしりと聳え立つのは会津駒ヶ岳。よく見ると一番高い会津駒のピークの左側に駒の小屋も見えます。次会津に来たら登ってみようかなと思い、この日から2週間後の7月に会津駒ヶ岳に登りに行きました。

巨大な池塘の向こうに広がる美しい稜線。平坦な山頂に湿原が広がる田代山を象徴するような景色だと思います。

チングルマとリンドウの隙間にオノエランが生えていました。花が開くのはもう少し先でしょうか。

田代山の看板が見えてきました。ここが頂上なのかと思いましたが、最高点は1,971mとされているので違いそうです。これだけてっぺんが平坦だと頂上という概念もあまり意味がないかもしれません。ここで左に曲がって帝釈山の方に向かいます。

大量のワタスゲが綿毛を付けており、足元から見上げるように写してみると画面を白いフワフワが埋め尽くします。

木道の隙間まで見逃すまいとワタスゲが群生しています。植物の生命力は目を見張るものがありますね。

湿原を歩いていると突如、壁のように目の前に現れる針葉樹林。真っ直ぐ進み中へ入っていきます。
オサバグサ咲き誇る帝釈山

林の向こうに田代山避難小屋があるのですが、休憩にはまだ早いのでまずは帝釈山に登ることにしました。

田代山から帝釈山への道は樹林帯の中に引かれた緩やかなアップダウンのある林道です。

道の脇にスッと立つ白く可憐な花はオサバグサ。

帝釈山に入った途端、すごい数のオサバグサが咲いていて驚きました。田代山では影も無かったので尚更驚きです。若干花が散り始めてはいますが至る所に咲いていて見応えがあります。

光量の限られた樹林帯の中に咲く白い花は儚くも存在感があります。

他にも何か咲いていないか探していると葉の影の方にイチヨウランが一輪だけ花を付けていました。乱獲で数を減らした希少な花で、この日初めて実物を見ることができました。萼片に紫色の斑点があるものが一般的なようですがこの個体には斑点が全く見られず全体的に色が薄めです。

帝釈山への道にも所々に木道があり、小さなお花畑が散在しています。

ミツバオウレンが地面を覆っていました。

この辺りにもオサバグサが群生しています。背の高い花が列を成して咲いている様は竿燈まつりや祇園祭のような華やかさがありました。

岩場に掛かるハシゴが見えてきました。ハシゴ場は二つあります。

木々の隙間を通っていきます。

ハクサンシャクナゲが咲いていました。これも田代山には咲いていなかった花です。隣り合う山同士でも植物にとっては全く異なる環境のようです。

二つ目のハシゴが見えてきたら頂上までもうすぐです。

最後の方の岩場は少し歩きにくいので焦らずゆっくり進みます。
帝釈山からの景色を満喫

帝釈山の頂上に着きました。

あたりをぐるっと見回してみればどこもかしこも山、山、山。山以外何も見えません。別天地に降り立ったような清々しい心地にしばし浸ります。


南方面を見ると日光連山が仲良く並んで聳え立っています。木々の合間を覗くと西の方には燧ヶ岳が顔を覗かせています。

田代山で見た会津駒ヶ岳も見えました。

ゆっくり景色を眺めていると馬坂の方から団体さんが上がってきたのでそろそろ田代山に戻ることにします。帝釈山の頂上はそこまで広くないので田代山の方でご飯でも食べようと思います。



花を眺めつつ一気に田代山に戻ります。帝釈山にはオサバグサを含めて白い花がたくさん咲いていました。


田代山避難小屋まで戻ってきました。小屋の中には弘法大師像が安置されています。宿泊すると弘法大師に見守られながら夜を越すことになるという、ご利益がありそうな小屋です。
復路も綺麗な山頂湿原

ご飯を済ませたら田代湿原を戻っていきます。湿原の復路は先述の通り一方通行の南側の木道を通っていきます。

群生するタテヤマリンドウも可愛らしいですね。


花の方のチングルマもまだ残っていました。綿毛が膨らむ前のチングルマは少し花の頃の面影があります。

湿原の東の方に高原山(釈迦ヶ岳)が見えました。那須岳の南、日光連山の東に位置し、アクセスが良いので登りやすく景色も良い山です。

ワタスゲを眺めながら歩いていきます。

こちらの道はハイマツ林の中を通り抜けるように引かれています。

田代山湿原の入り口に戻ってきました。ここからは元来た道を下るだけです。

ここで会津駒ケ岳とはお別れです。


小田代を通り森の中を下りていきます。階段のおかげで下りは楽々です。


川を渡って木々をくぐって登山口に到着しました。

下山した頃には駐車場は満車になっていて、道の途中まで車が溢れていました。アクセス困難な場所にも関わらずこれだけたくさんの人が訪れる辺り、田代山の人気のほどが改めて分かりました。
下山後の湯めぐり
山を降りたらお楽しみの温泉タイム。ということで湯ノ花温泉に来ました。星商店駐車場が共同浴場利用者の駐車場になっています。まずは共同浴場の利用券を買いに近くをウロウロ。平日昼間だからか旅館や民宿には人の気配がなく、駐車場近くの大山商店さんで利用券を手に入れることができました。


4ヶ所それぞれ個性あふれる浴場で楽しい温泉巡りでした。天神湯と石湯については源泉が直接注ぐ浴槽の下流にもう一つ小さい浴槽が設置されており、こちらのお湯は少し冷やされて入りやすくなっています。


次に来たのは木賊温泉。岩風呂の近くに駐車場があり、そこから川の方に下りていきます。温泉の入り口で300円を入れて利用する方式です。風呂は壁の無い開放的な造りになっており、川の流れる音を聞きながら温泉を楽しみました。
あとがき
田代山の存在を知ったのは山を登るようになってからでした。地図で調べてみても周りには曲がりくねった林道以外何もない真っ白な空白地帯で、こんな場所に何があるんだろうと思ってしまうようなロケーションです。しかし実際に山道を登り山頂湿原の景色を目の当たりにして、今までこれほど美しい場所が福島にあるのを知らなかったのかと衝撃を受けました。初めて山に登った時の感情を思い出させてくれるような山であり、福島の山にもっと登りたいという意欲を引き出してくれるような魅力を持った山でした。
公式サイト
花見朔巳 校訂『大日本地誌大系』第31巻,雄山閣,1932.8
『東北の山旅』,山と渓谷社,1958
舘岩村史編さん委員会 編『舘岩村史』第1巻(通史編),舘岩村,1999.3
館岩村史編さん委員会 編『館岩村史』第4巻(民俗編),館岩村,1992.2
田中澄江(1983)『花の百名山』文春文庫
畔上能力 編(2021)『山渓ハンディ図鑑2山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社
清水建美 編(2021)『山渓ハンディ図鑑8高山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社