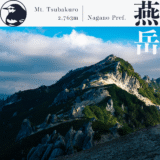栗駒山について
所在地:秋田県・岩手県・宮城県
山系:奥羽山脈
標高:1,626m
選定:花の百名山・日本二百名山
栗駒山は秋田、岩手、宮城三県の県境に位置する奥羽山脈の山。宮城県側から見上げる緩やかな山容とは裏腹に有史以降も活動を続ける第四紀火山であり、北西麓には栗駒山から西へと連なる外輪山や火山活動により生じた湿原や湖沼群などの入り組んだ地形が広がっています。春の山野草が美しく花の百名山に選ばれるほどの名所ですが、それ以上に栗駒山の名を世に知らしめたのは秋の紅葉が作り上げる景色です。「神の絨毯」とも称される栗駒山の紅葉は、山頂から始まって裾野へと広がり山全体を染め上げて、まるで紅葉に身を浸すかのような雄大な光景を見せてくれます。
南斜面の紅葉がよく知られる栗駒山ですが、天馬尾根を通って秣岳(まぐさだけ)の南に広がる白銀湿原(しろがねしつげん)にも是非訪れてみてください。緩やかな稜線沿いに広がる草原が黄色く染まり、風に吹かれてゆらゆら揺れるのどかな風景に癒されること間違いなしです。栗駒山周辺と比べて人も少ないのでゆったりとした時間を過ごすことができます。道中の展望岩頭では栗駒山北斜面や火口部の景色を一望できるのでここで一息入れていくのがおすすめです。
勅宣日宮駒形根神社



東麓の沼倉地区には勅宣日宮(ちょくせんひるみや)駒形根神社があり、山頂には駒形根神社奥宮(嶽宮)の祠が鎮座しています。社伝によると日本武尊東征の際に駒形嶽(現在の栗駒山)に大日孁尊・天常立尊・國常立尊・吾勝尊・天津彦番邇々藝尊・神日本磐余彦尊の六柱の神々を祀り山頂に奥宮、沼倉に里宮を創建したとされており、『延喜式』神名帳にも名を列する歴史深い神社です。坂上田村麻呂が東征に際して戦勝祈願し戦勝の後には四大門を建てて駒形大明神の額を奉納したといい、時代が下り源氏や平泉藤原氏にも篤く信仰されたといいます。平安時代中頃に駒形山大昼寺が建立され修験道場となりましたが江戸中期に神仏分離が進み神社に復して現在に至ります。

現在栗駒山に立つ駒形根神社の石祠は2023年に行われたクラウドファンディングを基に再建されたものです。石造りでありながら千木や鰹木などの緻密な意匠が光る立派な祠は一見の価値ありです。
いわかがみ平登山口~中央ルートについて
栗駒山(須川岳)・秣岳 / 白雀さんの秣岳・栗駒山の活動データ | YAMAP / ヤマップ
宮城、秋田、岩手のそれぞれに登山口があり登山ルートは9本もあるようです。今回は最もメジャーなルートであるいわかがみ平登山口を起点とした中央ルートで登りました。

中央ルートは前半部分が石畳で整備されており後半の登りも必要に応じて階段がつけられているので全道を通して歩きやすく、栗駒山までのピストンであれば普段登山をしない方にもおすすめできます。場所によっては露岩も見られるので靴底がしっかりした運動靴を用意すると良いと思います。

今回は栗駒山頂上を通過して西に2時間ほど歩いた先の秣岳にも登りました。栗駒山から先の道もよく整備されていますが滑りやすい場所や水が溜まる場所があるので雨の日などは通行注意です。この日は霧雨気味だったので秣岳に着く頃には靴が泥まみれになって大変でした。
紅葉シーズンにはいわかがみ平までの道が通行規制されて一般車通行止めになります。マイカーの場合は「いこいの村栗駒跡地臨時駐車場」に駐車してシャトルバスでいわかがみ平登山口に向かうことになります。交通規制の時期は年によって変わるので栗原市公式観光サイトで最新の情報を確認してください。
栗駒山は熊出没地域であり登山道上にも熊が現れることがあるようです。2025年には登山道ではないですが、いわかがみ平から約7kmの荒砥沢で熊による死亡事故が発生しており注意が必要です。東栗駒山や今回歩いた秣岳周辺など、栗駒山から距離がある場所は人が少ないので熊に出会う確率も高いと思われます。熊鈴やスプレーなどの対策をして複数人で登るようにしましょう。
いわかがみ平から山頂へ

栗駒山のシャトルバス乗り場です。午前6時の始発便ですが車内はほとんど満車でした。天気が悪い上に紅葉シーズンも終盤であるにも関わらずこの人出なので、見頃の時期は早めに来て並んでおいた方が良さそうです。

10分ほどでいわかがみ平に到着。見渡す限りの霧で展望も無いのでとりあえず登り始めます。

中央ルートの道は石畳で綺麗に整備されています。木のトンネルを潜って進むワクワク感が楽しいです。

視界が開けてきて紅葉している木も増えてきました。色々な木が混ざっていて赤、黄、緑のカラフルな道です。

斜面が見えてきましたがやっぱりガスでよく見えません。

こういう時は近くの葉っぱに目を向けます。コミネカエデは真っ赤に色づいていました。


ウメバチソウやツリガネニンジンなど夏の花がちょっとだけ残っていました。


この辺りから足元は赤や黒の岩が転がる火山らしい風合いに変わってきます。

緑色のササやハイマツが混じると紅葉の鮮やかさが際立ちます。

高度が上がり山頂手前に差し掛かると木が無くなり草紅葉が目立ちます。雲も徐々に晴れてきたので期待が高まります。


山頂に着きました。山の上はかなり開けていて奥宮の祠も近くにありました。晴れてくるのを期待して待っていたのですが再び雲が濃くなってきました。この日は結局最後までこんな感じの天気でした。
霧に包まれる天馬尾根の草紅葉

山頂の分岐を西の方に進み秣岳に向かいます。

霧に煙る紅葉というのも風情があります。

普通の曇り空だと色が綺麗に出ないことが多いのですが、葉っぱが霧に濡れると良い感じに色が出てくるというのもありがたいです。


天狗平に着きました。須川温泉への道は火山性ガス発生により通行止めになっています。

天狗平から10分ほど歩くと展望岩頭という外輪山南縁の見晴らしがいい場所に出ます。まだ霧が深いので帰りに期待です。


ここから先は険しい下りで泥濘も増えてくるので気が抜けません。秋冬用の防水性高めのズボンで来て助かりました。

秣岳の鞍部まで来ました。見晴らしの良いササ林が広がっています。

少し進むと木道が見えてきて白銀湿原に入ります。

秣岳の方は霧の中です。

湿原の北端の方に小高い岩山が立つ様から「山のモンサンミッシェル」と呼ばれているらしいです。確かに岩のお城のような感じです。


その岩山を越えて道は続きます。森の中をちょっと降ります。


秣岳の手前で再び道が開けてきました。この辺りにはオオシラビソが生えています。特徴的な紫色の球果(松ぼっくり)も付いていました。

緩斜面を登った先が頂上です。

ちょっと休憩して栗駒山の方へ戻ります。

白銀湿原の帰り道もきれいです。

霧に覆われて幻想的でした。

秣岳の鞍部まで戻ってきました。

改めて見上げてみると栗駒山への登りは結構険しい道のりです。
展望岩頭からの絶景

展望岩頭の辺りまで戻って来るとちょっとずつ雲が流れて栗駒山北西部に広がる火口周辺の地形が見えてきました。

展望岩頭から北西方向に見えるのが龍泉ヶ原。道の通っていない秘境です。右奥に見えるのは須川湖。ブナ林に囲まれた絶景スポットですが麓なのでまだ紅葉していないみたいです。

真北を向くと栗駒山火口に聳える剣岳と周辺に広がる湿原が見渡せます。色とりどりの木々がモザイク状に山肌を埋め尽くしており見ごたえがあります。

真北から東の方へちょっと視線を動かすと青緑色が鮮やかな昭和湖が見えてきます。その名の通り昭和19年(1944年)の水蒸気爆発で形成された火口湖で、かつては須川登山道を通って湖畔まで近づくことができたらしいですが現在は火山ガス濃度が高い状態が続いているため立ち入り禁止区域となっています。

西の方に広がる外輪山の岩壁も見ごたえがあります。


赤く染まる岩壁や尾根筋に立つ紅葉などバラエティに富んだ景色が魅力です。

展望岩頭の辺りからは栗駒山の山容も一望できます。北斜面が紅葉に埋め尽くされて真っ赤に染まる様は圧巻です。


栗駒山を登り返していきます。一瞬雲が途切れたので期待しましたが、やっぱり今日はずっとガスの中みたいです。

時刻は既に12時を回り栗駒山頂上には人がいっぱいいたので早々に中央ルートを下りていくことにしました。

登りでは見られなかった南斜面の紅葉です。山肌が紅葉に包まれているような絶景でした。登山道に行列ができている辺りから栗駒山の人気のほども伝わるでしょうか。


山道を抜けて石畳を過ぎたらイワカガミ平に着きました。ますます霧が濃くなってきたので早めに下りてきて正解でした。

駐車場に到着し下山完了です。
あとがき
秋の栗駒山は一日中曇り空でしたが綺麗な景色を楽しめました。こういう日は遠くの山が完全に見えなくなるので今登っている山そのものを楽しめる気がして良いものだと思います。南側の山肌を埋め尽くす紅葉と北斜面の岩壁や湿原に広がる紅葉の対比も栗駒山の美しさの一つなので是非展望岩頭辺りまでは足を延ばしてみると栗駒山を更に楽しめるのではないかと思います。
次は春の花が咲く時期を狙って登り栗駒山のまた違った魅力を味わってみたいところです。
公式サイト
栗原郡教育会 編纂『栗原郡誌』,臨川書店,1986.6.
『宮城県神社名鑑』,宮城県神社庁,1976.
畔上能力 編(2021)『山渓ハンディ図鑑2山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社
林将之 著(2020)『山渓ハンディ図鑑14増補改訂樹木の葉実物スキャンで見分ける1300種類』山と渓谷社