
会津駒ヶ岳について
所在地:福島県
山系:越後山脈
標高:2,133m
選定:日本百名山・東北百名山
会津駒ヶ岳は福島県檜枝岐村に位置する山で、山頂部に広がる大湿原と稜線が織りなす牧歌的な景色が登山者を惹きつけて止まない会津の名峰です。草原に覆われた複数のピークが緩やかに稜線で繋がり列を成すような山容が特徴で、駒ヶ岳から中門岳にかけての稜線歩きでは木道が敷かれた登山道をゆったり歩きながら抜群の展望と湿原に咲く花々を楽しむことができます。
大湿原と夏の花々

夏の会津駒ヶ岳は花の楽園、登山口から頂上まで多種多様な花が咲き競う様は圧巻です。会津駒ヶ岳を代表する花として知られるのはハクサンコザクラで、山頂湿原の至る所で群生を見ることができます。

そして今回の登山で特に目立ったのはイワイチョウでした。多雪地域の亜高山〜高山帯の湿原に多く分布するイワイチョウにとって、森林限界を超えた先に湿原が広がる会津駒ヶ岳は絶好の環境のようです。
檜枝岐村の鎮守「駒形大明神」

檜枝岐村では古くから駒ヶ岳と燧ヶ岳に対する信仰が篤く、弘仁七年(816年)駒ヶ岳山頂に駒形大明神を、天長九年(832年)燧ヶ岳山頂に燧大権現を祀ったという伝承が残っています。現在でも駒ヶ岳山頂から南に500mほどの所にある駒ノ大池の畔には駒形大明神の祠が鎮座しています。
会津駒ヶ岳の魅力が広く知られるようになると、近隣の尾瀬や帝釈山脈などと同様に多くの登山客が訪れるようになりました。尾瀬は日本における環境保護活動の先駆けとなった山域としてよく知られるところですが、会津駒ヶ岳においては村一丸となって環境保全に取り組んできたことが特筆すべき点といえます。その詳細については下記の福島県公式HPをご覧ください。
当時の人々には湿原の脆弱性に関する知識が普及されておらず、踏圧被害によって湿原の裸地化が発生しました。
そこで自発的に保全活動をはじめたのが檜枝岐村です。今から約50年前、昭和40年代になると檜枝岐村は木道を敷いて被害を食い止める保全活動を始めました。

また村内の鎮守神社には駒形大明神、燧大権現の二柱が村の鎮守神として鎮座しており、例祭では江戸時代からの伝統芸能である檜枝岐歌舞伎が奉納歌舞伎という形で披露されています。南会津町の大桃地区にも駒ヶ岳を祀る駒嶽神社が鎮座しており、こちらの境内にも大桃の舞台と呼ばれる歌舞伎舞台が現存します。
駒ヶ岳は狩猟生活の時代より人々の生活を支えてきた恵みの山であるとともに村の鎮守として人々の信仰を集め伝統文化を見守り続けてきた、檜枝岐村の文化や生活と深い関わりを持つ山です。
滝沢登山口ルートについて
今回は最もメジャーなコースである、滝沢登山口から会津駒ヶ岳の先に聳える中門岳まで登るピストンコースで登ります。下りで南西の大津岐峠方面に向かいキリンテ登山口に下りるコースもあるので、復路で別な道を歩きたい場合はこちらを選ぶのもありです。今回はマイカー利用ということもありピストンにしました。
国道から2kmほど林道を登った先の滝沢登山口には駐車場がありますが、キャパシティが20台ほどなので早朝に到着しないと停められないかもしれません。林道の路肩にも何台か駐車できますが、それでも空きがない場合は国道沿いの村営駐車場に駐車可能です。
駒の小屋まで高低差1000mほどの急登で体力を削られますが、そこさえ越えれば気持ちのいい稜線歩きになります。危険箇所は特にありませんが、ソールの状態によっては傾斜した木道が滑りやすいかもしれないので注意してください。特に駒ヶ岳山頂西面は樹林帯となっており木道が湿っている箇所が見受けられました。駒ヶ岳山頂を過ぎて稜線に出ると日光を遮るものが無くなるので日焼けや熱中症対策は万全にしていきましょう。
会津駒ヶ岳・中門岳 / 白雀さんの中門岳・会津駒ヶ岳の活動データ | YAMAP / ヤマップ
急登を越えて湿原へ

朝の滝沢登山口駐車場です。まだ5時半ですが既に結構車が停まっていました。


車道を進んで滝沢登山口に着きました。

登山道は最初から急な登りです。木の根が露出している部分も多いので滑らないように注意していきます。

今回は新しい靴の初舞台(近場の低山には何度か登りましたが)ということもあってウキウキです。ザンバランが2024年に発売したモデルのサラテトレックです。

ツルッとした小石や岩の主張が強めの登山道だったのでソフトでグリップが効く履き心地のサラテトレックには最適でした。



道の前半のブナ林には山でお馴染みの花が色々咲いていました。

2kmほど歩くとオオシラビソやダケカンバが目立ち始めます。

この辺りから見晴らしが良くなり、木々の向こうに駒ヶ岳の稜線が見えてきました。


花の方も高山植物らしい面々に変わってきました。最初の急登で一気に高度を上げるので目まぐるしい植生の変化が楽しめます。


イワイチョウも姿を見せ始めました。遠目にみるとなんてことは無い小さな白い花のようですが、近づいて見てみるとツンと尖った花弁の縁と中心部がフリルのように波打つ精緻な構造が見て取れます。


しばらく歩くと山道が木道に変わります。木々の間を抜けると視界が開けて湿原に出ます。

イワイチョウ咲く道を歩いていきます。
駒の小屋から駒ヶ岳登頂

小高い丘の上に建つ三角屋根の駒の小屋。絵に描いたようなのどかでメルヘンな世界観に、まるでファンタジー世界に迷い込んだかのような気分になります。ここまで2時間の疲れも一気に吹き飛ぶ景色です。


見渡す限りの草原の中でチングルマは風になびき、池塘の辺りにワタスゲが揺れる。いつまでも見ていられそうな風景でした。

駒の小屋を横目に見つつ、まずは駒ヶ岳の方に向かうことにしました。小屋正面にある駒ノ大池にもワタスゲが揺らめいていました。

池の畔には駒形大明神の祠が立っているのでお参りしていきます。

このあたりからハクサンコザクラが咲き始めます。

駒の小屋の北の方に見えるピークが駒ヶ岳です。木道は駒ヶ岳の西面に続いていきます。


駒ヶ岳に近づくにつれてササが目立つようになってきました。駒の小屋と駒ヶ岳の間の鞍部を登っていくとササ群落の向こうに針葉樹林が見えてきました。

駒ヶ岳の西面まで来たら木道は林の中です。木陰である上に梅雨明け直後ということもあってか木道が湿っているので滑らないように気をつけて歩きます。新調した靴はアプローチシューズ寄りの滑りにくいソールなのでこういう木道でも安心して歩けました。


右に曲がって駒ヶ岳山頂方面に進み、森の中に通された階段を登っていきます。



会津駒ヶ岳山頂に着きました。山頂周辺ではハクサンシャクナゲやナナカマドがたくさん咲いていました。

木々の隙間にカメラを向けている方がいたのでそちらを見てみると、3つ4つ折り重なった稜線の先のはるか遠くに富士山のシルエットが浮かび上がっていました。会津駒からこんなに鮮明に見えるんですね。
絶景の稜線をたどり中門岳へ

山頂を通過して中門岳方面に向かいます。駒ヶ岳の北面は視界が開けて尾根沿いに広がる湿原が見えてきます。

さらに進んで雪田草原まで降りていくと中門岳へと続く登山道が一望できます。3つのピークの右が中門岳です。道のりは2kmほどでアップダウンもほとんど無いのでここからは楽しいハイキングです。


1つ目のピークの手前は雪解けが遅いのか新芽が目立たず地面がまだまだ茶色でした。もう7月ですがわずかに雪が残っています。

木道の隙間にショウジョウバカマが一株顔を覗かせていました。

1つ目のピークを越えると緑輝く夏らしい景色になってきます。草原のあちこちに見えるピンク色の塊はハクサンコザクラの群落です。もうちょっとハクサンコザクラの写真を一杯撮りたかったのですがこの時は望遠を持ってこなかったので遠景しか撮れませんでした。不覚。

天気に恵まれたおかげで池塘の群青色も一際鮮やかです。


2つ目のピークの周辺にはモウセンゴケやツマトリソウなどここまで見かけなかった花も現れ始めました。


池塘もバリエーション豊かで見ていて飽きません。

2つ目のピークと中門岳の鞍部には中門池という一際大きな池塘があります。周囲を覆い隠すように針葉樹林が並んでおり、日本庭園さながらの箱庭的美を感じる風景です。


池の畔を通りササ林を抜けたら中門岳はすぐそこです。

中門岳の頂上につきました。池塘の周りを一周するように木道が敷かれています。池の中にポコポコ浮かぶ浮島が愛らしいです。

池塘越しに眺める駒ヶ岳。風が止んできたので水面に空が写って爽やかな風景です。

ワタスゲはまだ朝露が乾いていないようでしんなりしていました。

中門岳の北端の方に来ると池塘越しに燧ケ岳の山容がきれいに見えます。会津駒から見た燧ヶ岳はまさに「猫の耳」といった感じの見事な双耳峰です。尾瀬によく行く方からすれば尾瀬ヶ原から見上げる厳つい印象とはかなりギャップがあるかもしれません。
復路の景色も楽しみつつ下山



中門岳の景色を楽しんだので来た道を戻ります。緩やかな登り返しなので来た時より少し体力を使います。

往路では気づきませんでしたがコバイケイソウの隙間にミヤマキンポウゲが咲いていました。7月以降も色々な花が咲きそうです。

幾つかのピークを越えて駒ヶ岳の麓に戻ってきました。帰り道は駒ヶ岳の西面に回り込んで駒の小屋に向かうので頂上へ登り返す必要はありません。画面中央辺りで木道が右に分岐しているのでそちらに進んでいきます。

駒ヶ岳周辺のオオシラビソ林を通り過ぎた辺りの景色です。駒の小屋と燧ケ岳のツーショットもいいものです。ずーっと遠くの方には頂上で見た富士山が再び姿を現しました。

一息に駒の小屋まで戻ってきました。山バッジと飲み物を買いベンチに座ってしばし休憩。

パンを食べながらぼんやりしていたら近くに生えていたコバイケイソウの一株が蕾を付けていることに気づきました。コバイケイソウの見ごろは7月下旬以降なので花を付けるには大分早いです。

今回はピストンルートなので滝沢登山口へ下りていきましょう。

帰り道の展望も見事でした。真正面に見えるのが6月に登った田代山と帝釈山です。
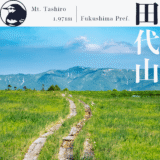 【東北】田代山・帝釈山〜猿倉登山口から春の山頂湿原へ〜【6月】
【東北】田代山・帝釈山〜猿倉登山口から春の山頂湿原へ〜【6月】

少し進むと画面中央に男体山や女体山、右の方にポツンと聳える日光白根山が見えてきます。

振り返って丘の上に建つ駒の小屋の風景を再び目に焼き付けます。

名残惜しいですが湿原を抜けて下りの樹林帯に入っていきます。



ベニサラサドウダン、アカモノ、クロヅルなど登りで見逃していた花が結構ありました。かなりの急登だったので花を見る余裕がなかったみたいです。


森の中を下り続けて1時間半ぐらいで登山口に戻ってきました。
あとがき
1ヶ月前に田代山に登った際に「次は会津駒ヶ岳に登ろう」と決めて梅雨明け直後の蒸し暑い日に檜枝岐村まで来たのですが、山頂までの急登は案の定カンカン照りの汗ダラダラで大変な道のりでした。しかし樹林帯を越え尾根伝いに広がる大湿原を目の当たりにすると疲れもすっかり忘れてしまい、眼前の絶景に夢中になりながら稜線歩きを楽しみました。「天上の楽園」の魔力は伊達では無いと身をもって思い知らされる充実した山行となりました。
公式サイト
『桧枝岐村史』,桧枝岐村,1970
環境省生物多様性センター(2009)1/25,000植生図「会津駒ヶ岳(あいづこまがたけ)」
畔上能力 編(2021)『山渓ハンディ図鑑2山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社
清水建美 編(2021)『山渓ハンディ図鑑8高山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社


