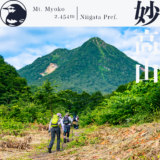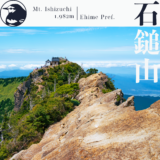一盃山について
所在地:福島県郡山市
山系:阿武隈山地
標高:856m
選定:新うつくしま百名山
一盃山は阿武隈高地の一座で、郡山市東部、小野町との境に位置しています。その名の通り盃を伏せたような山容と、1時間程度で登頂できる手軽さが特徴です。山頂は大きな広場になっているため、地元では遠足やピクニックで訪れる里山として親しまれているようです。南の田母神方面に開けており、頂上近くの「音の岩」からは蓬田岳や大滝根山、二ッ箭山など阿武隈山地南部の名峰を一望することができます。
馬場登山口コース
一盃山 / 白雀さんの一盃山の活動データ | YAMAP / ヤマップ
登山口は馬場と黒甫の二つありますが、ヤマップの地図には馬場登山口コースのみ線が引かれていたのでこちらで登ることにしました。低山でも雪山であることには変わりないので、登る人が多くてルートが安定している方で登るのが安牌だろうという判断です。楽に登れる山で危険個所などは特にないですが上述の「音の岩」あたりは雪に埋もれていると滑落のリスクもあると感じたので、冬に登る際は注意してください。今回の山行では積雪量10~20cm程度の場所がほとんどでしたが、音の岩のあたりは雪が溜まるようで膝上まで雪が積もっていました。冬はゲイターを付けて登った方がよさそうです。
馬場登山口から頂上へ

駐車場に車を停めて、一盃山の案内看板からスタートです。



のどかな農村を抜けて、未舗装の道に出たら本格的な登山道に入っていきます。

杉と笹の広がる道を歩いていきます。杉林の合間に雪を踏む音だけが広がる静謐な雰囲気に心が癒されます。


杉林も笹林も見慣れた光景のはずなんですが、雪の中で眺めることでまた違った魅力が見えてきます。積もった雪が光を反射してディテールを浮き上がらせているようです。

登りの斜度もそこまできつくないのでツボ足でどんどん進んでいきます。杉林を抜けるとブナやコナラなど落葉樹を主とした雑木林に入ります。

音の岩の方に進んでいきます。

7時を過ぎて日が照ってきました。あんまり暖かくなると道が緩くなるのでちょっと急ぎます。

雪道には逆光が映えますね。


笹の葉が朝陽を浴びて黄金色に輝いていました。


すっかり太陽が昇って明るくなりましたが、やっぱり逆光ばっかり撮ってしまいます。

踏み跡一つない雪面に落ちる影が神秘的です。

陽光が一筋の踏み跡に影を落とす様も魅力的です。四方八方を被写体に囲まれて身動きが取れなくなりそうです。

誘惑と闘いながらなんとか頂上に到着。

頂上からは中通り南部とその向こうまでずっと見渡せました。遠くの山は日光連山でしょうか。
音の岩で眺望を楽しむ

トレースは音の岩に続いています。まるで手招きするようにこちらを指す木の影がミステリアスな気配を漂わせています。

歩き出したはいいものの雪がすごく深くて膝まで雪で埋まってます。これはトレースが無ければなかなか大変でした。先に登った方に感謝です。

音の岩に着きました。


東側の左手前に見えるのが日陰山、右のほうにいわきの二ツ箭山や水石山が見えます。南の方には少し見にくいですが蓬田岳が見えます。登ったことのある山が増えてくるとこうして眺めているのもさらに楽しくなります。

朝ごはんにカップ麺を食べました。登山で大分汗をかいたので塩分補給です。

帰りは同じ道です。雪道だと往復で影の具合がまるっきり変わるので新鮮な気持ちで歩けます。

山頂の広場は「大志の広場」というそうです。冬は広い雪原になっていますが、雪の無い時も来てみたいですね。

弾けた後のウバユリの朔果が残っていました。花だけでなく実もまた目を引く造形です。冬はこうした花の名残も見られるのが楽しいところだと思います。

山頂付近はクヌギやコナラが多いのか林の色が濃いめです。雑木林と一口に言っても場所によって結構印象が違います。

復路は西の方がよく見えます。北西の遠くに見えるのがおそらく吾妻連峰です。


どんどん下ります。杉の木に見惚れつつ進みます。

杉林を抜けました。正面には蓬田岳が見えます。

田んぼを横目に見ながら下山完了です。
斎藤の湯上の湯

帰りは三春の名湯、斎藤の湯に行きました。上の湯と下の湯に毎回交互に入っているのですが今回は上の湯でした。施設はレトロな湯治場という感じですが清掃が行き届いており清潔感のある印象です。泉質は阿武隈地方で散見されるラジウム鉱泉の沸かし湯で、10分ぐらい浸かると体が芯まで温まるので冬の登山後に最適です。
あとがき
一盃山は阿武隈山地の中央部という位置関係と、綺麗な盃状の山容により素晴らしい景観を有しています。登山道には山場らしい山場はないので山に慣れた方には少し物足りないかもしれませんが、空いた時間にゆるく登って今まで登った山を眺めながらのんびりとした時間を過ごすのもいいものだと思います。また、低山でも冬になると景色が一変して新鮮な気分で登ることができるので、厳冬期の冬山は登らないという方にも今回のような里山スノーハイクはおすすめです。
公式サイト
林弥栄 監修(2021)『山渓ハンディ図鑑1野に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社